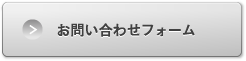交通事故の「後遺障害」とは、事故によって負った傷害が治療を続けても完全には回復せず、身体や精神に一定の障害が恒久的に残ってしまった状態を指します。治療を続けた結果、それ以上の回復が見込めないと医師により「症状固定」と判断された後に残っている症状が、日常生活や仕事に支障を及ぼす程度であれば、「後遺障害」として認定される可能性があります。
後遺障害にはさまざまな症状があり、たとえば視力や聴力の低下、手足のまひ、関節の可動域制限、慢性的な痛み、外見の変形、さらには高次脳機能障害なども含まれます。これらの障害の程度や内容に応じて、「後遺障害等級」という区分が設けられており、1級から14級までの等級が設定されています。等級が高いほど重度の障害とされ、賠償金額も大きくなります。
後遺障害と認定されるためには、医師の診断書や検査結果などの医療資料に加え、被害者自身の陳述書や日常生活の支障を示す証拠などを基に、自賠責保険の「損害保険料率算出機構」による審査を経る必要があります。この認定が損害賠償請求の基礎となるため、適正な等級が付されることが極めて重要です。
後遺障害が認められると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償請求が可能になりますが、保険会社との交渉で争いになることも多く、専門的な知識が求められます。適正な補償を受けるためには、弁護士などの専門家に相談することが有効です。