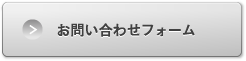交通事故における「空走時間」とは、運転者が危険を認知してから実際にブレーキを踏むまでの時間のことを指します。この間、車両は何の減速もせずに走り続けており、そのため「空走(くうそう)」と呼ばれています。空走時間は人間の反応速度に依存し、一般的には0.7秒から1.5秒程度とされていますが、状況や個人差によって大きく変動します。
たとえば、運転中に前方の歩行者や障害物を発見した瞬間、運転者がそれを危険と判断し、ブレーキを踏む決断をするまでには一定の時間がかかります。この判断と行動の間に車は進み続けており、この進んだ距離は「空走距離」と呼ばれます。空走時間が長くなればなるほど、この空走距離も長くなり、結果として事故の回避が難しくなります。
空走時間は交通事故の過失割合や回避可能性の判断にも重要な要素です。たとえば、「運転者は事故を回避できたはずだ」とされるかどうかを判断する際には、空走時間とその間に進んだ距離が具体的に検討されます。また、飲酒や疲労、スマートフォンの操作などによって空走時間が長くなる傾向があるため、そうした行為は重大な過失とみなされることがあります。
交通事故を防ぐためには、空走時間をなるべく短くすることが重要であり、そのためには前方への注意を怠らず、常に危険を予測する姿勢が求められます。空走時間の短縮は、安全運転の基本のひとつです。