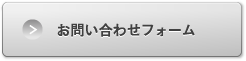交通事故の「むちうち」とは、主に自動車事故、とくに追突事故などで首に急激な前後の衝撃が加わることによって起こる首周辺の障害の総称です。
正式な病名ではなく、医学的には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などと診断されることが一般的です。
衝撃の瞬間、首がムチのようにしなる動きをすることから、むちうちと呼ばれています。
むちうちの症状には、首や肩の痛み、こり、可動域の制限のほか、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれ、倦怠感など、さまざまなものがあります。
事故直後は興奮状態や緊張のために痛みを感じにくく、数日経ってから症状が現れるケースも多いため、軽い事故であっても注意が必要です。
治療は、安静、投薬、リハビリ、物理療法などが中心となり、症状の程度や回復状況に応じて数週間から数か月続くこともあります。
ただし、画像検査では明確な異常が確認できない場合も多く、症状が自覚的なものにとどまりやすい点が特徴です。
そのため、保険会社との治療費や慰謝料の交渉、後遺障害認定をめぐってトラブルになることも少なくありません。
交通事故後に首や体に違和感を覚えた場合は、早めに医療機関を受診し、継続的に治療と通院記録を残すことが重要です。
むちうちは見過ごされやすい一方で、日常生活や仕事に長く影響することもあるため、適切な対応が求められます。